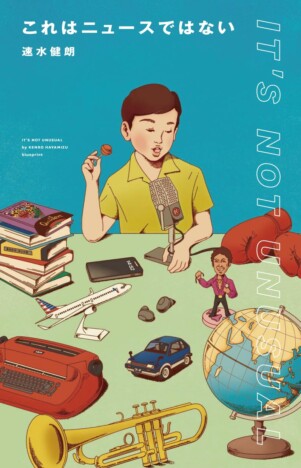荻野洋一の『母よ、』評:痛覚にうったえかける、最も現代的な映画

人はいったい何を求めて映画を見に行くのだろう? 娯楽か、暇つぶしか、それとも人付き合いか。結論から言えば、なんだっていいわけだが、時に人は、楽しむためにではなく、もがき苦しむために映画を見に行くことがある。たとえば、イタリアの映画作家ナンニ・モレッティの新作『母よ、』がそうだ。お断りしておかなければならないのは、ストレスの解消にも、楽しい気分にもならないことだ。それどころか、よりストレスを自家薬籠中のものとするために見る映画だと言っていい。この映画の作者であるナンニ・モレッティが立派なコメディ作家であり、この『母よ、』にもどこか風刺喜劇のユーモアさえ漂わせているにもかかわらずだ。
では、そんな映画を見る必要があるのか? ──その答えは「ある」であり、いや現代ではますますその必要性が高まってさえいる。私たち観客は、この映画によってストレスを直視することを求められる。ふだん使わない筋肉を使うよう強いられる。というのも、私たちは自分たちの生活の中で、直視しなければならないストレスを見て見ぬふりをしているからだし、甘受しなければならない苛酷な現実から目をそらしているからだ。

イタリアの首都ローマの各所で撮影された、わずか1時間半あまりのこの映画は、工場を解雇された大勢の従業員たちのデモ行進に、公安部隊が放水して応戦するシーンから始まる。さすがはキャリアを通じて反権力をかかげ、右派のシルヴィオ・ベルルスコーニ政権とも激しく対立し続けたナンニ・モレッティ監督の面目躍如とも言うべきホットな幕の開け方だ、などと感心していると、女性の「ストップ!」というかけ声が聞こえて、それが合図となってデモも放水もしゅんと止んでしまう。映画のロケ撮影だったのである。集団のアクションにストップをかけた監督の女性こそ、本作の主人公マルゲリータ(マルゲリータ・ブイ)であるわけだが、彼女の撮影現場がどうやらあまりうまく行っていないらしいことは、部外者である私たち観客にもすぐにわかる。社会派の女性映画作家として鳴らした彼女の創作活動は、どうやら曲がり角に来ているようだ。彼女はその現実にさいなまれる。
だが彼女は、それ以上の問題を抱えている。母親の心臓病が悪化し、医者は死の日が遠くないことを覚悟せよ、彼女と彼女の兄(ナンニ・モレッティ自身によって演じられている)に告知する。日に日に弱っていく母親(ジュリア・ラッツァリーニ)。
彼女のもうひとつの問題──それは中学生の娘のことだ。離婚した元夫のもとで暮らしているらしい娘は最近、恋をし、悩んでいたが、マルゲリータは娘から悩みを相談されなかった。自分にも厳しいが、他人にも厳しく当たるマルゲリータのことを、周囲の者は多かれ少なかれ敬遠しているのだ。

私たち観客は、映画の上映時間のあいだじゅう、このマルゲリータという女性映画監督のアイデンティティ・クライシスにお付き合いしなければならない。痛い。にがい。ヒリヒリする。しかし、痛覚にうったえかけるこの映画は、最も現代的な映画である。つまり、すっかり生きにくくなった現代に必要な映画だからである。主人公の問題、母の問題、兄の、娘の、撮影スタッフの、俳優たちの問題。高額なギャランティでアメリカから招いた脳天気なイタリア系移民の俳優(ジョン・タトゥーロ)とマルゲリータは最初そりが合わなかったが、このアメリカ人スターにも彼なりに向き合い続けている問題があることがわかってくる。
それら複数の問題は、互いにからみ合い、問題の宇宙を形成している。そしてこの宇宙の中に私たち観客もまた、どっぷりと浸かっていることに気づくはずだ。危機のもとに置かれおののき続ける彼女は私たちのことであり、母親の看病のために仕事さえ辞めてしまう兄──彼も私たちである。そして最終的には、記憶が薄れ、衰弱し、死にゆく母親さえも、私たち自身の肖像にほかならない。
人間なんて、生まれて成長して、しばらく悩んだり楽しんだりしたら、もう死期が近づいてくる。実に短く、はかないものだ。でもそこには、記憶があり、愛(や憎しみさえ)があり、そして、敬意があるとき、そのはかないとも思える人間の一生が、ほのかに輝くのがわかる。

主人公の母親は、高校のラテン語教師だった。「ラテン語文法なんて学んで、なんの役に立つの?」と問いかける中学生の孫娘にむけて、ラテン語を学ぶことの大切さを優しく説いてみせることが、この年老いた女性の最後の仕事だ。高校の卒業生たちが母の家に何人も訪ねてきて、元ラテン語教師への敬愛の念をしゃべっていく。「先生は、私たちにとっても母だったんです」と卒業生たちが語るのを聴くのは、非常に感動的だ。この時、母親が、他人の言葉を通して、娘や息子とのあいだに築いていたものとは異なる宇宙をかいま見せているからだ。
だからといって、この映画がいっさいのストレスから解放されるわけではないことは、文頭にも書いたとおりである。あらゆる問題はまだそこにあり続け、登場人物はそれをひとつひとつ解決に努める必要がある。それはちょうど、この映画を見るために劇場に入る前に私たち観客が、ありとあらゆる問題を抱えていて、上映が終わって席を立った瞬間からふたたびそれらの問題のもとへと戻っていくのと同じように──。
人生が問題への対処の中にこそ存在すること、そしてその対処の中に真の美があることを、この『母よ、』というイタリア映画は語り、そして私たちを後押しし、私たちと共にあろうとする。